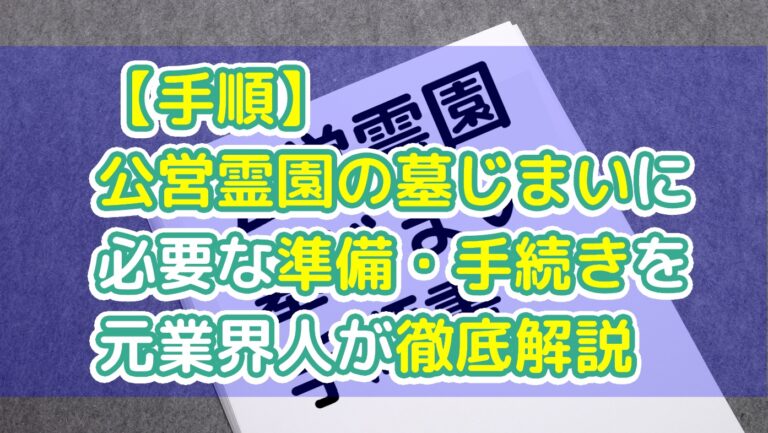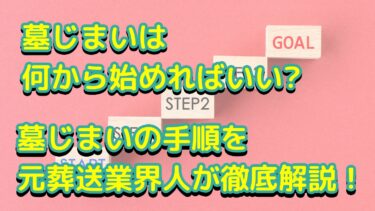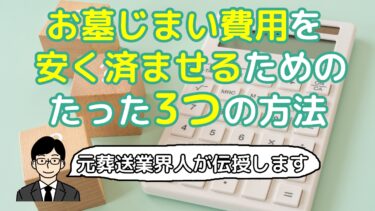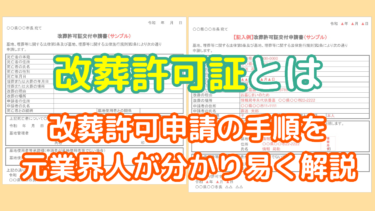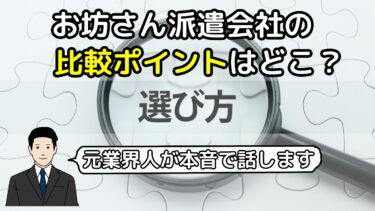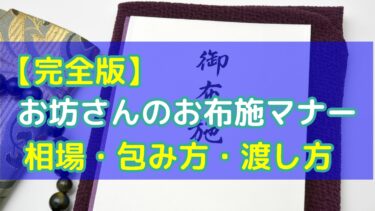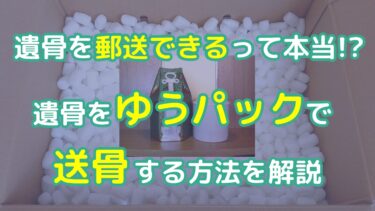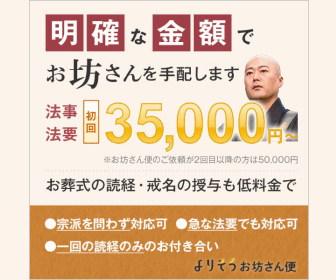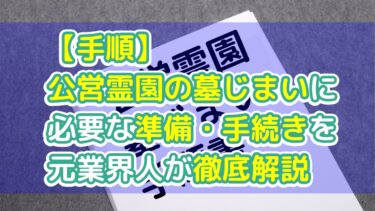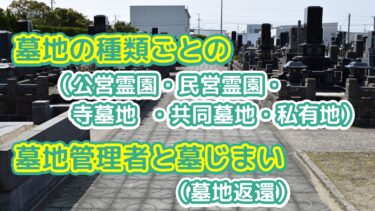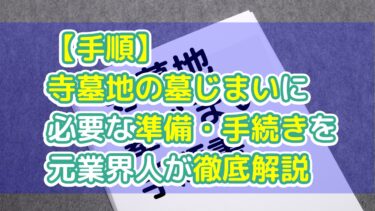この記事は公営霊園にお墓をお持ちで墓じまいを検討されている方向けの手順書になっています。
- 墓じまいをしたいけど何から手をつければいいか分からない
- 墓じまいをするには何を準備すればいいか分からない
- 墓じまいの手順・流れを知りたい
お墓じまいは準備や手続きが大変というイメージがあるかと思いますが、整理をしてみると意外と簡単です。
これから解説する手順に沿って進めていけば、1ヵ月程で墓じまいを完了することもできます。
- 公営霊園にお墓が建っている方
- お墓じまいを何から始めれば良いか分からない方
- お墓じまいの準備を進めたい方
私がお墓じまいの相談を年間2,000件以上引き受けていた経験に基づいて解説しますのでかなり実践的な内容になっています。
お墓じまいを「何から始めれば良いか悩んでいる」という方はぜひ本記事を参考にしてもらえれば幸いです。
編集長「こまど」の実績
- 年間10,000件以上の葬送サービスのご相談を対応
- 年間2,000件以上の「墓じまい」のご相談を対応
- 年間300件以上の「墓じまい」を施行
お墓じまいの手順は墓地の種類によって異なりますので、公営霊園以外にお墓をお持ちの方は下記のページからあなたのお墓がある墓地を選んでご覧ください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。お墓じまいは「色々と手続きややらなくてはいけないことが複雑で大変」というイメージがあるかと思います。ですが内容を整理をしてみると、やらなくてはいけ[…]
公営霊園とは

公営霊園とは地方自治体である都道府県や市区町村が運営管理している墓地です。
ほとんどの場合、公営霊園には「霊園管理事務所」というものがあります。
お墓の承継手続きや改葬許可申請、お墓の工事申請や墓地の返還手続きといったことは霊園管理事務所で行います。
ただし、一部の公営霊園では霊園管理事務所が無く、市区町村役場がそれを担っていることもあります。
その公営霊園がある市区町村役場へ問合せてみてください。
公営霊園の墓じまいの手順

公営霊園に建っているお墓の墓じまいをする時は、下記の手順に沿って進めていくとスムーズです。
- 遺骨の改葬先の永代供養墓や納骨堂を探す
- 墓地の承継手続きをする
- 墓じまい工事費用の見積りを取る
- 改葬先の契約をする
- 改葬許可証を取得する
- 見積りを取った中から工事を依頼する石材店を決める
- お墓の閉眼供養(魂抜き)の日取りを決める
- 墓じまいの工事申請をする
- お墓の閉眼供養(魂抜き)を行う
- 工事着工&遺骨を受け取る
- 「工事完了届」の提出
- 墓地の返還手続きをする
- 遺骨を改葬先へ納骨する
1.遺骨の改葬先の永代供養墓や納骨堂を探す
公営霊園に建てたお墓の墓じまいをするには、まずお墓に納骨されている遺骨をどこに移すか決めることが必要です。
墓じまいの工事費の見積りを取るだとか、改葬許可証を取得するだとか色々やることはありますが、肝心の改葬先を決めておかないことにはお墓じまいをしても遺骨の行き場に困ってしまいます。
主な改葬先は下記の3つのいずれかになります。
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 別のお墓
費用の安さ重視であれば「永代供養墓」が一番ですね。
私がお手伝いをしたお客様でも、お墓じまい後は遺骨を永代供養墓へ改葬される方が一番多くいらっしゃいました。
永代供養墓のメリット・デメリットについては下記の記事を参考にしてください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。永代供養墓(えいたいくようぼ)というとどんなイメージがあるでしょうか。最近は霊園でも永代供養墓を取り扱っているようですが、一昔前までは「永代供養墓[…]
2.墓地の承継手続きをする
このステップは不要な方もいます。
墓地の承継手続きとは、墓地の契約者を変更する手続きになります。
既にあなたが墓地契約者であればこのステップは飛ばしていただいて構いません。
墓地の契約者が亡くなった時に行うことが多いですが、存命のうちに行うこともできます。
お墓じまいの手続きは墓地の契約者しか行うことができません。
例えば、墓地契約者だったお父さんが亡くなったので墓じまいをしたいという場合。
子供が墓じまいの手続きをすることになりますが、その前にお父さんから子供へ墓地の承継手続きをしてからでないと墓じまいの手続きはできません。
墓地契約者がお亡くなりになられた場合は霊園管理事務所へ連絡し「墓地の承継手続きをしたい」と伝えてください。
3.墓じまい工事費用の見積りを取る
改葬先を見繕ったら墓じまい工事費用の見積りを取りましょう。
いくら見積りが安くても、改葬先が決まっていなければ意味がないので手順としてはこの順番になります。
見積りの有効期限は大抵1ヵ月~3ヵ月です。
見積りを先に取ってから改葬先を探すとなると、有効期限が切れてしまい再見積りで金額が上がるということにもなりかねません。
「墓じまい工事費用を安く済ませる方法」については下記の記事に詳しく書いていますので、併せて読まれることを推奨いたします。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。「お墓じまい費用を少しでも安く済ませたい!」そんなお声にお応えして、元葬送サービス業界でお墓じまいのお手伝いをしていた私がお墓じまい費用を安く済ま[…]
遠方にある墓地で、「あなたが現地に行かずに見積りを取る方法」については下記の記事を参考にしてください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」の編集長のこまどです。お墓じまいをしたいという相談で一番多かったのが、お墓が遠方にあってお墓参りに行くのが難しいというものでした。遠方にあるお墓の場合、墓じまい費用の[…]
4.改葬先の契約をする
墓じまい工事費用について、納得いく見積りが出てきたら改葬先の契約をしましょう。
墓じまい工事費用の見積りを取る前に改葬先を契約してしまうのは危険です。
もしも工事費用が予算オーバーな金額で墓じまいそのものが難しくなった場合、改葬先の契約金が無駄になってしまいます。
改葬先との契約は改葬許可申請をするまでにすれば大丈夫です。
したがって、改葬先の検討→墓じまい工事費用の見積り→改葬先の契約→改葬許可申請の順で行うのがベターです。
5.改葬許可証を取得する
改葬先の契約が済んだら改葬許可証を取得しましょう。
改葬許可証の取得手続きのことを「改葬許可申請」と呼びます。
改葬許可申請書には改葬先を書く欄があります。
また、役場によっては改葬先との契約書の写しか、改葬先の「受入証明書」というものが必要になります。
こういった事情から、改葬許可申請をする前に改葬先との契約を済ませておく必要があるわけです。
改葬許可申請の詳しい手順については下記の記事を参照ください。「受入証明書」についても詳しく解説しています。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。お墓じまいを検討されている方は「改葬許可証(かいそうきょかしょう)」という言葉を聞いたことがあるかと思います。でも「具体的な取得方法についてはイマ[…]
なお、墓地契約者が無くなっている場合はステップ2の「墓地の承継手続き」を済ませていないと改葬許可申請ができませんのでご注意ください。
6.見積りを取った中から工事を依頼する石材店を決める
改葬許可証を取得したら、工事を依頼する石材店を決めます。
このステップは特に解説することは無いですね。
見積りを取った中から一番安い石材店にするか、対応が良かった石材店にするかなど、あなたの基準で選定してください。
7.お墓の閉眼供養(魂抜き)の日取りを決める
改葬先の契約も済んだ。改葬許可証も取得した。工事を依頼する石材店も決めた。
これで後は墓じまい工事をするだけと思いきや…まだ準備があります。
それがお墓の閉眼供養の日取り決めです。
お墓を解体したり移動させる場合には、「閉眼供養(へいがんくよう)」というお経をお坊さんに挙げてもらう必要があります。
※閉眼供養は「魂抜き(しょうぬき)」とも言います。
菩提寺がいる場合は菩提寺に閉眼供養をお願いしてください。
基本的に閉眼供養は菩提寺の都合に合わせて調整することになります。
菩提寺がいない場合は「お坊さん派遣(僧侶派遣)サービス」を利用するのがいいでしょう。
お坊さん派遣(僧侶派遣)サービスとは、菩提寺がいない非檀家向けのサービスで、低額&明朗価格でお坊さんを派遣してもらえるサービスです。
もちろん、このサービスを利用したからといって派遣されたお坊さんの檀家になる必要はありません。
派遣サービスを利用する場合は、基本的にあなたの都合で日程調整をすることができます。
オススメの派遣サービス会社については下記の記事を参考にしてみてください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。一昔前は画期的だと思われたお坊さん派遣(僧侶派遣)サービスですが、今では多くの派遣会社が存在します。そうなると困るのは選択肢が多くてどのお坊さん派[…]
8.墓じまいの工事申請をする
閉眼供養(魂抜き)の日取りが無事に決まったら、墓じまいの工事申請をします。
申請先は霊園管理事務所になります。
事前に霊園から「工事着工届」と「工事完了届」と「墓地返還届」という書類をもらっておきましょう。
※「工事完了届」についてはステップ11で解説します。
※「墓地返還届」についてはステップ12で解説します。
「工事着工届」には工事期間を書く欄があるため、先に閉眼供養の日取りを決める必要がありました。
というのも、閉眼供養を済ませてからでないと工事ができないからです。
石材店と相談し、閉眼供養以降の日取りで工事期間を決めましょう。
霊園によっては「工事着工届」に石材店の署名・捺印が必要なことがあります。
その場合は、自分で埋められる箇所を全て埋めた工事着工届を石材店に渡して置き、石材店が霊園に提出するという方法も可能です。
また、霊園によって着工日当日に「工事着工届」を霊園に提出すればOKなこともあれば、着工日の1週間前までに霊園に提出しておかなくてはいけないこともあるので要注意です。
9.お墓の閉眼供養(魂抜き)を行う
閉眼供養(魂抜き)は必ず工事着工前に済ませます。
閉眼供養(魂抜き)当日はお坊さんとあなた、もしくはお坊さんとあなたと石材店が同席する形になります。
お坊さんに閉眼供養(魂抜き)のお布施を払うことになるので用意していきましょう。
お布施の相場と包み方・渡し方のマナーについては下記の記事で詳しく解説しています。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。ご葬儀や法事・法要、お仏壇・位牌・お墓の開眼供養(魂入れ)や閉眼供養(魂抜き)など、お坊さんにお願いをしてお布施を渡す場面は多岐に渡ります。場[…]
10.工事着工&遺骨を受け取る
無事に閉眼供養(魂抜き)も終えたらいよいよ墓じまい工事着工です。
工事着工後に遺骨を受け取る場合は、予め石材店に「何時くらいにお墓まで遺骨を取りにくればいいか」を聞いておきましょう。
というのも、お墓によってはある程度お墓を解体しないと遺骨を取り出せないこともあるためです。
既に閉眼供養(魂抜き)の時に遺骨を持ち帰っている場合や、遺骨は石材店に郵送してもらう場合はあなたが工事に立ち会う必要は基本的にありません。
「遺骨が郵送できるの?」と不思議に思われた方はぜひ下記の記事もお読みください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。突然ですが、あなたは「遺骨は郵送できる」ということをご存じでしょうか。遺骨の郵送方法を知っていると下記のような場合に役に立ちます。 遠方[…]
11.「工事完了届」の提出
「工事完了届」とはその名の通り、工事が完了したことを伝えるために霊園に提出する書類です。
「工事完了届」の提出方法は霊園によって下記の3つのいずれかになります。
- 工事完了後、石材店が霊園に提出する
- 工事完了後、あなたが霊園に提出する
- 工事着工届と一緒に提出
石材店が霊園に提出する場合
最も多いのが「石材店が霊園に提出する」パターンです。
この場合は石材店に任せておけばOKです。
予め石材店に「完了届を提出し終わったら一報ください」と伝えておけば問題ないでしょう。
あなたが霊園に提出する場合
この場合はあなたが霊園に「工事完了届」と「工事完了後の墓地の写真」を併せて提出することになります。
そのため、石材店に完了後の墓地写真をもらったら霊園管理事務所の窓口へ提出に行くか、郵送で提出しましょう。
工事着工届と一緒に提出している場合
この場合は既に書類を霊園に提出してある状態なので、霊園に「工事が終わりました」と電話をすればOKです。
12.墓地の返還手続きをする
墓地の返還手続きとは、「墓じまい工事が完了したので墓地を霊園にお返しします」という手続きです。
この手続きをするために「墓地返還届」を霊園に提出する必要があります。
「墓地返還届」も霊園によって下記の3つのいずれかの提出方法になります。
- 石材店が「工事完了届」と一緒に提出する
- 石材店が「工事完了届」を霊園に提出後、あなたが霊園に提出する
- あなたが「工事完了届」と「墓地返還届」を一緒に霊園に提出する
石材店が「工事完了届」と一緒に提出する場合
石材店が墓地返還届も一緒に提出してOKな霊園であれば、石材店に任せておけばOKです。
予め石材店に「返還届を提出し終わったら一報ください」と伝えておけば問題ないでしょう。
石材店が「工事完了届」を霊園に提出後、あなたが霊園に提出する場合
この場合は石材店から完了届を提出したという連絡をもらった後、もしくは完了届を受け取った霊園からあなた宛に連絡があった後に「墓地返還届」を提出することになります。
提出方法は霊園管理事務所の窓口へ行くか、郵送での提出となります。
あなたが「工事完了届」と「墓地返還届」を一緒に霊園に提出する場合
この場合はあなたが「工事完了届」と「墓地返還届」と「工事完了後の墓地の写真」を併せて提出することになります。
そのため、石材店に完了後の墓地写真をもらったら上記の3点を持って霊園管理事務所の窓口へ提出に行くか、郵送で提出しましょう。
13.遺骨を改葬先へ納骨する
ステップ12までで既存墓地については無事に墓じまいが完了しました。
最後はお墓から取り出した遺骨を改葬先に納骨すればOKです。
改葬先が遠方のために送骨をする場合や、石材店がお墓から取り出した遺骨を直接改葬先へ送骨する場合には、事前に改葬先へその旨を伝えておきましょう。
※改葬先によっては送骨での受け取りができないこともありますので、必ず事前に確認しておきましょう。
送骨とは遺骨をゆうパックで郵送することです。
「遺骨が郵送できるの?」と不思議に思われた方はぜひ下記の記事もお読みください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。突然ですが、あなたは「遺骨は郵送できる」ということをご存じでしょうか。遺骨の郵送方法を知っていると下記のような場合に役に立ちます。 遠方[…]
まとめ
公営霊園の墓じまいについては、上記で解説した手順通り進めてもらえば非常にスムーズに終えることができます。
他に聞きたいことがある方や、手順は分かったがオススメの改葬先や石材店を紹介してほしいという方は下記のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。